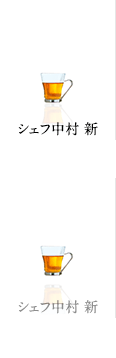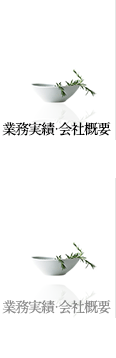最注目「今月の逸品」 vol.
12
日本・さしすせそばなしー醤油編

小豆島の醤油
もの作りにはそれに欠かせない道具が大切だ。農家ならさしずめ鍬(くわ)や鋤(すき)、鍛冶屋なら鎚(つち)といったところか。黒酢造りには壺や甕が重要な役割を果たしている。
今回は桶と醤油の話である。
この桶と言う文字。読み方はもちろん「おけ」であるが、ここ小豆島では「こが」と呼ぶ。語源についてはどうもまだ調べがつかないが広辞苑に出ているというのだから由緒正しい。ここからは桶という文字が出たら、「こが」と読み進んでいただきたい。
瀬戸内海に浮かぶ牛を横から見たような形の「小豆島」。人口は30000人強。その密度は198人(㎢あたり)で、岐阜県の195人より多い。かつてから映画「二十四の瞳」で有名であり、古の建物も多く残るノスタルジックな環境が、熟年の旅行者の心をひきつける。
ここ小豆島は瀬戸内海性気候の恩恵を受け、降水量が少なく、比較的乾燥した温暖な地域だ。そう聞くとのんびりした人々が住まいしているのかと言うとそうでもなく、コツコツと努力することを厭わず、商いに対して積極的に取り組む気風がある。
この島は大坂(昔の大阪)と大きな関係がある。太閤さんが大坂城を作る際に必要とした石はこの地からも切り出され、かつ対岸の赤穂と並んで良質の塩を作っていたこともあり、大坂と船を用いた移出入が盛んとなった。
この製塩業と海運業がここに大きな産業をもたらすことになる。
醤油造りだ。キッコーマン、ヤマサ、ひげたと並んで大手醤油メーカーの一角を成すマルキンもここ小豆島にあるほど。島の収入を支える重要な産業なのである。
船は、西(九州)から麦と大豆を運び、東からは紀州の醤油技法と灘の酒を運ぶ樽を持ち込んだ。当然のように醤油造りがおこるのだが、その後、江戸時代に幕府直轄地、つまり「天領」に指定されたことで大きく発展し、一時は400を数える醤油醸造屋がこの島に集まった。ある意味で緩い規律の中で成長してゆくために、中には粗悪なものも出始める。これを問題視し、ついに自分たちの手で厳しい決まりごとを制定。それに漏れるところを排除して品質を守った。明治維新以降は税金が課せられるようになり、徐々にその数を減らしてゆくこととなる。戦争による食糧統制というさらに厳しい時代を切り抜けた醤油造りは現在20軒。ここで興味深いのは、大きな醸造会社から規模が小さく頑固な蔵元まで、それぞれ全てにきちんとした個性があるということだ。つまり、一般的に産業が廃れてなくなってゆく要因となる過疎や競争力の低下などでその数を減らしたわけではなく、自らの手で厳しく戒めながら時代に沿う製造業を営んできた結果であり、それは淘汰と呼ぶより、研ぎこまれた結果だと表現してよい。つまりこの20軒は醤油造りの精鋭たちなのである。
ここで醤油の造り方を簡単に説明しておかねばならない。まず、蒸して柔らかくした大豆と小麦を合せたところに麹菌を混ぜ、醤油麹をつくる。これに塩を加えて槽に入れ発酵を促し、醪(もろみ)を経てからしっかり絞る。こうして出てきた黒い液体が醤油である。醤油製造の大きな仕事は仕込みと圧搾、そして容器に詰める作業であり、酒造りから比べると仕事が少ない。
醤油そのものの味が強調されるのは、仕込みから6ヵ月を経たものであり、それを過ぎさせて保存すると次第にその強さは弱まり、こなれた味へと変化してゆく。いわゆる熟成である。本当に醤油そのものの強さが出るのは6ヵ月程度のもので、大手メーカーはこの点に留意するため、熟成する前に商品化してゆく。その方が安く販売できるうえに、個性がはっきりと表現できるからである。一般市場での競争力という点に於いて一石二鳥というわけだ。もちろん大手メーカーは近代的な設備で管理され、仕込槽も管理が容易いものとなる。
正金(しょうきん)醤油。
小豆島でかたくなに杉製の桶を使った醤油造りを続けている由緒あるところだ。桶の容量は540ℓ。昔風にいうと三十石だ。関西にとってこの三十石という単位は大きな意味を持つ。江戸時代初期から、今の大阪と京都の伏見を結ぶ淀川に三十石船という船便があった。その名の通り、三十石分だけ運べる中型の船である。三十石という単位は一つの運送の目安であったばかりではなく、人々が抱く満足の「容」(かたち)でもあったのだ。
正金醤油を訪ねたのは秋から冬に変わろうとする11月上旬。凛とした空気に包まれた仕込み蔵は、その日のひんやりさと重なって荘厳ささえ感じるほど力強く存在した。
三十石を蓄える24の桶たちは元々灘の酒蔵から譲り受けたものなのでひとつひとつの形が微妙に違う。それを大工さんの巧みな技で全て建物と一体化するように建てつけられている。多くの醤油醸造場では桶と桶は分かれていて、その間の移動には渡し板を使用するものだ。しかし、正金醤油にはそれがない。いわば建物そのものが桶なのだ。
この大きな桶の壁には数々の微生物が住む土壁は表現の言葉に迷うほど重々しく、杉材全てが赤銅色。漂う力強い醤油の香りは全身をつつみ、来る者を蔵から離そうとしない。多くの醤油蔵を見てきたが、これほど「美」を感じるところは初めてである。ほんとうに美しい。
肝心の醤油となると、これが「飲める」。トロリとした食感の後にほんのりとした甘味と熟した旨味が重なりあい、ほどほどの余韻をもって喉を通る。大手メーカーによくあるような豆の強さを感じることはない。
当主の藤井さんのおっしゃる「うちの醤油は、料理の土台となる調味料です。出過ぎず、控え過ぎず」の言葉通りだ。特に一度使った醤油もろみを使用する再仕込醤油は、底力があって旨い。魚が豊富に獲れる島で生まれた醤油らしく当然刺身に合うのだが、是非ともこれは小魚の煮つけに使いたい。メバル、ガシラ(カサゴ)などの小さい根魚の味は繊細にして鮮明。強い豆の味が勝つような醤油で煮つけては存在感すらない小魚の煮つけも、この二段仕込み「匠」にかかえれば、魚の嬉嬉とした生き様を感じるまでに昇華させる。
この素晴らしい醤油の造り手である藤井さんのお兄さんは、佐賀で著名な自然農法家である。元々そのお兄さんがこの蔵を継いだのだが、「野菜で人を救うのだ」と一念発起して転業。大成された。その後を任されて「本当はそんなつもりではなかったのですが」と前置きしつつ、「このラベルは兄が残してくれたデザインなのです」と優しく醤油瓶を撫でながら、この日初めて私の前で目を線のようにして笑った。
人生、醤油の味と同じく、「出過ぎず、控え過ぎず」のようである。